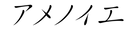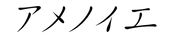山一の「中華せいろ」
山一の「中華せいろ」
無水鍋と一緒に、山一の「中華せいろ」を使って蒸し料理をつくってみました。
最初は少しハードルが高いかなと思っていたせいろですが、実際に使ってみると驚くほど手間いらず。
好きな食材をいれて、タイマーさえかけておけば他の調理にも集中できます。
油跳ねなどが無いのでキッチンが汚れることもなく、可愛らしい見た目はそのまま食卓の主役にもなり、洗いものも少なく済むので大変助かりました。
また、無水鍋と同様に、「蒸す」ことで素材本来のおいしさを引き出してくれます。
せいろの中は100°C以上になることがないため、焦げる心配がなく、素材に余計な負担をかけないそうです。
さらに、蒸すだけで調理できるため、基本的に油を使う必要がありません。
油を控えられて、野菜はかさが減るからたくさん食べることができ満足感も。
そんなせいろは、健康志向の私にもぴったりのアイテムでした。
 抜群の耐久性と良質な素材
抜群の耐久性と良質な素材
近年、台湾製や中国製の安価な中華せいろが市場に多く出回る中、山一では国産檜材を使用し、職人の手仕事によって製造を続けているといいます。
素材として使用される檜は、樹齢100年以上の原木を中心に活用されています。
それらを四層に重ねて厚みを持たせることで、抜群の耐久性を実現しているのが特徴。
また、蓋の上部には竹網代編みを二重に重ね、適度に蒸気を逃し、水滴が食材に落ちるのを防ぐ工夫が施されています。
繊維が細かく丈夫で、ふちに厚みがあるため強度にも優れ、長く愛用できる名品となっています。
 使いやすさ
使いやすさ
山一の中華せいろは、中国製の中華せいろのように身の上下にツメが無いため、身の高さが低く食卓で料理を取り出しやすくなっています。
また、蓋に高さがあり、ふわりと盛り付けた蒸しものや皿蒸しも可能で、料理の幅を広げてくれます。
食材はごろっと楽しみたいので、高さを気にせず使用できるのは嬉しいところ。
朝食をワンプレートにすると、支度は簡単に、せいろならではの華やかさも楽しめますね。
サイズは、21cmは家族2人〜3人用、24cm以上は家族3人〜4人用におすすめとのことで、私は21cmのものを愛用しています。
 使い初めに
使い初めに
使用前のお手入れも忘れずに。
水またはぬるま湯をせいろ全体にまんべんなく流しかけ、十分に濡らしてから使用します。
乾いた状態で鍋にかけると焦げる場合があるので、注意が必要です。
 蒸し野菜
蒸し野菜
朝食だけでなく、せいろを使ってさまざまな料理に挑戦してみました。
今の時季は、やはり緑鮮やかな春野菜が欠かせません。
そこで、蒸し野菜を作ってみることに。
じっくりと火を通す「蒸し料理」は、味や栄養、使いやすさに優れた調理法です。
時間が経っても美味しく食べられるので、保存しておけば次に使うときには味をつけるだけで手軽に楽しめます。
保存がきくため、蒸した食材を次の日の忙しい朝には朝食やお弁当のおかずとして活用することも。
野菜は蒸すことでかさが減るので、たくさん食べることができ、満足感も得られますよ。
茹でるよりも栄養価が高く、炒めるよりヘルシーに仕上がるため、つい頼ってしまいます。
 手作りのほくほく焼売
手作りのほくほく焼売
せいろはお肉を調理するのにもうってつけ。
特に、せいろで作る焼売は、電子レンジでは出せないふんわりとした柔らかさと、ぎゅっと詰まった肉汁がたまりません。
蒸し器から立ち上るふわっとした湯気を眺める時間や、蒸し上がりに広がる檜の豊かな香りは、心がほっと和みます。
市販の焼売も手軽で美味しいですが、一度手作りの味を覚えると格別で、晩酌のお供にも最高です。
 蒸気の力で、身体を整える
蒸気の力で、身体を整える
お家で食べる料理は自然とシンプルなものに惹かれるもの。
お湯を沸かして、食材を入れて蒸気で蒸すというシンプルな方法は、疲れて帰宅した身体や心に、ほんの少しの余裕をもたらしてくれます。
蓋をかけた瞬間、食材が顔をのぞかせる光景を一緒にいる人と共有するのも、せいろならではの小さな贅沢。
静かに季節がほころぶ今、大切な人とゆったりと過ごすきっかけに、是非皆さんも取り入れてみてください。