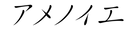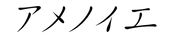小さな高揚感とともに
小さな高揚感とともに
新しいうつわを手に入れた日。
包みをほどいて、うつわをそっと手に取るあの瞬間に、ふわっと心が踊ります。
光の加減で釉薬がきらりと光ったり、手のひらに沿うやわらかな丸みにふれてみたり。
うつわを眺めながら、何を盛ろうか、どんなふうに使おうかと想像するだけで、気持ちがふわりと浮き立ちます。
ただの道具なのに、出会ったばかりのうつわが、これからの食卓の景色を少し変えてくれそうな気がして。
そんな予感が、静かに心を弾ませてくれるのです。
 うつわにそっと気持ちを寄せる「目止め」の時間
うつわにそっと気持ちを寄せる「目止め」の時間
陶器のうつわを迎えたとき、まず最初に行うのが「目止め(めどめ)」という作業です。
お米のとぎ汁や小麦粉を溶いた水にうつわを浸し、あらかじめ水分やでんぷん質を含ませることで、使い始めの染みや油分、色素の吸着、さらにはヒビや割れなどを防ぐ効果があるとされているそう。
陶器には、見た目には分からない小さな穴(気孔)が無数にあり、そのまま使うと、料理の汁気や油分が、うつわの中にじんわり染み込んでしまうことも。
とくに白や生成りのうつわなどは、シミになりやすいため、あらかじめ「目止め」をしておくと、より長く美しく使い続けることができるのだとか。
焼きもののことを総称して「陶器」と呼ぶことがありますが、
実際には「陶器」と「磁器」の2種類があり、それぞれ取り扱い方が異なります。
目止めが必要なのは、磁器ではなく、素地に吸水性のある「陶器」の方。
少し得意げに語ってしまいましたが、実は先日の買い物のとき、工藝ショップの店員さんが丁寧に教えてくださいました。
「このうつわは陶器なので、最初に目止めをしてあげると、長く気持ちよく使えますよ」
そうやさしく添えられたひと言が、うつわと向き合う時間の大切さをそっと教えてくれたように感じました。
 【基本的な目止めの方法】
【基本的な目止めの方法】
①うつわとうつわ全体が浸かる量の米のとぎ汁を鍋に入れます
②15~20分ほど弱火で煮沸します
③鍋ごと冷まし、よく洗い、充分に乾燥させます。
目止めが難しい場合は、まずたっぷりのお水に半日から一日ほど浸し、水分をふき取ってからご使用ください。
作家さんや窯元によっては、すでに「目止め済み」の場合もあるので、購入時に確認するのがおすすめです。
こうして手をかける時間は、実用的な意味だけでなく、
“このうつわと丁寧に暮らしていきたい”という想いを、自分にそっと伝える小さな儀式のようにも感じます。
とぎ汁に浮かぶうつわを眺めながら、このうつわとこれからどんな時間を過ごすのかを、ぼんやり想像してみたり。
「朝ごはんのプレートにしようかな」とか「友人を招く時に使いたいな」とか。
そんなふうに、手をかけることでうつわへの気持ちが少しずつ近づいていく。
「目止め」という作業は、うつわを守るだけでなく、自分の心をそっと整えるための、静かな時間でもあるのかもしれません。
 うつわとの時間が、暮らしを少しだけやさしくしてくれる
うつわとの時間が、暮らしを少しだけやさしくしてくれる
目止めを終えて、よく乾かしたうつわを棚に戻すと、まだ一度も使っていないのに、どこか前よりも“自分のもの”になったような気がします。
少しだけ距離が縮まったような、不思議な親しみ。
これからこのうつわで、どんな日々が積み重なっていくのだろう。
朝のトースト、ひとりごはんの焼き野菜、友人を招いた日の盛りつけ…
特別な日も、なんでもない日も、うつわは静かにそばにいてくれる存在です。
たった一度、数分の手間をかけるだけで、
道具への向き合い方や暮らしへのまなざしが、少しだけやさしく、丁寧になる。
そんな気づきをもらえるのが、「うつわを迎え入れる日」なのかもしれません。
ただ買って使うだけではない、
“ともに時を重ねていく”という選び方が、暮らしの輪郭をそっと整えてくれる。
今日迎えたうつわと、これからの毎日に、あたたかくて静かな時間が流れますように。