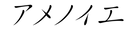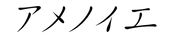漆器で迎える、心安らぐ新年度
漆器で迎える、心安らぐ新年度
気づけば4月。
桜が満開となり、春の植物たちが顔を出し始めました。
再びこの空気が巡ってきたと思うと時の流れを感じ、どこか安心した気持ちに包まれます。
新しい年度の始まりに、そんな安堵感に似たやわらかな「土直漆器」のうつわたちが届きました。
伝統的な日本の文化を感じさせるうつわたちは、淡い桜の香りが漂うこの季節によく似合います。
うつわの中で美しく息づく春の味覚を、贅沢に心ゆくまで堪能したいですね。
 土直漆器
土直漆器
鯖江市河和田地区で、1500年前に始まったとされる越前漆器。
時代に合わせて多彩な漆器づくりの展開を見せてきた河和田は、国内の外食産業用・業務用漆器の主要な生産地の一つです。
そんな地で培われた漆器製作の技術を活かし、土直漆器は1962年に創業しました。
こちらでは、素地作りを除くすべての工程を一貫して手掛けているそうです。
お写真を拝借して、制作現場をみせていただきました。
工房内には一級技能士と伝統工芸士が在籍しており、専門の職人たちがそれぞれの役割を担いながら、細やかな意思疎通を図りつつ作業を進めています。
このようなプロセスにより、製品の完成度が高まり品質が安定するといいます。
精度と美しさを追求する土直漆器は、手にした瞬間に心地よい安心感が広がります。
 朝の静寂を漆器から
朝の静寂を漆器から
せっかくなら、飯碗、汁椀、お盆を一日の始まりに。
朝から忙しい日々が始まると分かっていると、意識して静かな時間を持ちたくなります。
そんなときは、土直漆器の器で食卓の印象を引き締めるとちょうどいい余白が生まれます。
うっとりするような滑らかさは、自然と手で触れたくなりますね。
丸盆は木地に布を貼り、その上から漆を塗る「布着せ」という技法が用いられています。
布着せによって木地の割れや変形が防がれ、耐久性がアップするのだそう。
漆の層の下にほのかに浮かぶ布地の繊維が、独特の質感と深みを生み出しています。

欅の美しい木目を残し白漆を塗った飯碗「白」は、ベージュに近いやわらかい色味。
ゆるやかな曲線が美しい初々しさのあるフォルムは、現代のテーブルにすっと溶け込んでくれます。
 異素材とも調和を生む
異素材とも調和を生む
黒っぽい色が年を経るごとに青く変化していくという組椀(中)の「紺」は、その落ち着いた色合いが他の器と調和し、互いの美しさを引き立てます。
少し新鮮な印象を受けますが、不思議と統一感のある空間に。
たっぷり入るので、具沢山のお味噌汁やスープなど、汁椀としても使用しています。
華やかな陶器や色鮮やかな食材と合わせることで、洗練されたバランスが生まれ、食卓に豊かな表情を与えてくれますよ。

組椀はサイズ違いのものを重ねることもできるので、コンパクトに収納できます。
限られた収納スペースでもすっきりと整理でき、取り出しもスムーズです。
 春の味覚を輝かせる
春の味覚を輝かせる
さらっとした質感、やさしい色合い、しなやかな曲線が融合する土直漆器。
今回は春の恵みを詰め込んだ和食を盛りつけましたが、漆と欅がもつ自然で豊かな表情は和洋どちらの食卓にもよく馴染みます。
季節が変わるこの時期は、暮らしの中での新たなスタート。
新たな季節の訪れとともに上品な漆器を手に取り、心を整えながら穏やかな一日をはじめてみませんか。