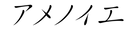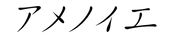旬を味わう
バタバタとしているうちに、今年も残りわずか。
今年一年を振り返り来年の目標を立てたり、部屋の大掃除やお正月の準備をしたりと、駆け抜けてきた日々の中で一度立ち止まり、自分自身や身の回りの環境にじっくり向き合う時期です。
特に年末年始の食卓は、家族や友達、パートナーと今年の出来事を分かち合い、心おきなく素直になれる尊い空間。
そんなこの季節に、大活躍してくれるのがお鍋です。
みんなでテーブルを囲み、お鍋の蓋を開ける瞬間にわくわくし、それぞれのタイミングで好きな具材に手を伸ばし、旬の食材を共有して堪能することで、どこか心の距離が近くなるように感じます。
人の輪の中心に来るお鍋は出番が多いので、折角なら特別なものを使いたいです。

土鍋を求めて伊賀へ
土鍋と言えば伊賀焼、伊賀焼と言えば土鍋と聞きます。では実際に他のやきものと何が違うのでしょうか。詳しく調べてみることにしました。
国指定の伝統工芸品「伊賀焼」は、奈良時代の発祥とされ、伊賀の歴史から巧みな技術と「用の美」としての在り方が紐解けます。
伊賀の周辺には陶土と薪が豊富に揃っており、中世には本格的に擂鉢や甕、壺などが焼かれました。
安土桃山時代になると茶陶として名を馳せますが、その後は一時衰退。18世紀に入り、京都や瀬戸から陶工を招き、日用のうつわが作られるようになります。

伊賀焼
かつては琵琶湖の底だったといわれる伊賀地方は、耐熱性に優れた粘土が採れることで知られています。
その土を用いて作る陶器は、高温で焼成される過程で、土の中に含まれる有機物が燃え尽きることにより無数の穴があきます。
その穴があることで耐熱性に優れ、一度火が入ると冷めにくく、熱を均等に伝えることができるため、土鍋や焼き物の素材として最適で、耐久性が高く、丈夫で長持ちします。
伊賀の気孔ができた多孔質な生地は、“呼吸をする土”と言われるほどの粗土で、遠赤外線効果が高く、食材の芯までじっくりと熱を伝えてくれるそうです。
この土地独特の土があるからこそ、伊賀焼の土鍋が今の地位を確立しているんですね。
長い歴史と技術を継承してきた職人たちによって守られてきた伊賀焼の土鍋。素朴で温かみのあるデザインの中に土の質感の力強さが感じられ、使い込んでいく程に味わいも増していきます。耐熱性の高い実用的な土鍋は一家に一台あると重宝されそうです。
食材の旨味を引き出してくれる優れた特性を持つ伊賀焼は、生活に密着した用途のものが多いため、もしかすると皆さんもどこかで一度は使ったことがあるかもしれません。
 カネダイ陶器 父の想いを受け継ぐ
カネダイ陶器 父の想いを受け継ぐ
今回土鍋を探している中で、そのような特別な素材が採れる伊賀焼の産地、三重県伊賀市丸柱にある「カネダイ陶器」さんへお伺いすることにしました。
こちらは1872年創業の、150年続く窯元で、現在の当主は大矢明日香さんです。
以前は四代目の父・正人さん、母・宏子さん、明日香さんの三人で分業を行い、小さい頃から正人さんの背中を見て育ってきたそうです。
2021年6月に正人さんが急逝したことがきっかけで、仕上げを中心に担当していた明日香さんは、成型も習得するために轆轤の勉強をするべく信楽窯業技術試験場に一年間通い、今では当主として母と二人三脚で家業を継ぎ、作陶に励んでいます。
当時について振り返りながら、「父の背中を見てきたので、それに尽きます。」と明日香さん。
必要な道具も揃っており、制作過程を見てきた幸せな環境に恵まれていたにもかかわらず、自分の気持ちで途絶えてしまうのはもったいないと感じたそうです。
宏子さんの「一回やってみよう」という言葉で目が覚め、今までとは違う新たな感情が生まれたといいます。

カネダイ陶器×アメノイエ
今回、カネダイ陶器さんには、「7寸鍋」と「行平鍋」の二種類を制作いただくことに。
7寸土鍋には、伊賀焼ではおなじみの「天目釉」と呼ばれる鉄分を多く含んだ光沢感のある黒色が施されています。
伊賀はもともと良質な鍋土が採れるため、伊賀土100%で、ペタライトが含まれていません。
ペタライトが入ると天目釉が使用できず、現在のような色味や質感を実現することができないそうです。
また、ペタライトを入れることで熱を加えても割れにくいという利点はありますが、熱が急に入るため、食材の良さを生かしきれているとは言い難い。
それに比べて、伊賀の土鍋はゆっくりと火が入るため、本来の食材の味を生かした美味しい鍋料理を楽しむことができます。

目止め
長く大切に使うためには、土の特性上、使用上の注意を意識しておきたいところです。
使い始める前に、目止めと呼ばれる作業は欠かせません。
残りご飯と水少々で、ご飯がノリ状になるまで炊き(弱火〜中火)、表面がふつふつとし、とろっとしたら火を止め、一晩そのまま置いておきます。
翌日、鍋の中身を捨て、洗ってよく乾燥させたら、完了です。
目止めをすることで、土鍋の底にひびが入っても水漏れを防ぎ、安心して使用できますね。

日本の鍋料理
目止めが完了したら早速調理に取り掛かり、はじめは寄せ鍋を作ってみることにしました。
底部が濡れていないかしっかりと確認し、火をつけます。最初は弱火でじっくりと温め、あたたかさが持続するので強火にはせず、中火で火を止めておきます。
旬の白菜や人参、さらに豚肉、豆苗、豆腐、しめじ、しいたけと野菜たっぷりで栄養満点。スタンダードですが間違いなく、手間もかからず美味しく仕上がり、生姜を入れると身体も心もぽかぽかに。自然とお酒も進みます。

出汁の効いたおでん
冬といえばおでんも忘れずに。旬の大根は少し大きめに。
一番好きな具材の話で盛り上がり、取り分ける際に自然とコミュニケーションが増えるのもお鍋の醍醐味ですね。
また、「カネダイ陶器」さんの土鍋は温かい状態を保ってくれるので、温め直しもあまり必要なく助かっています。
お鍋料理はレシピのバリエーションが豊富なのも嬉しい点です。
他にも、すき焼き、しゃぶしゃぶ、もつ鍋、スンドゥブ、海鮮たっぷりのエスニック風鍋など、定番から変わり種まで、季節や気分に合わせて心向くまま作りたいですね。

今年の終わりに
気が付くと急に寒くなった12月。四季を彩る食材に助けられ、やわらかな日差しとあたたかい広がりを求めて、移りゆく景色に身をゆだねながら、ちゃんと冬を愉しんでいたようにおもいます。
お鍋は、そんな冬の良いところを凝縮したような存在。
やさしくて滋味深く、自然と心をほぐしてくれます。
皆さんも、今年の終わりに大切な人とぜひお鍋を囲んでみてはいかがでしょうか。
カネダイ陶器さんの「行平鍋」も現在制作していただいており、来年届く予定なので、とても楽しみです。
届いたらまたコラムを通してご紹介させてください。
来年はどんな職人さんと出会うことが出来るでしょうか。世の中の変化や需要に合わせながらも、昔からの技術でものづくりに丁寧に向き合う職人さんたちやその作品に触れ、自分の心が動く瞬間が多く訪れる一年になりますように。
皆さんも、良い年をお迎えくださいませ。