
宮島のしゃもじを訪ねて
木のしゃもじとの出会い 先日友人の家で見た木のしゃもじが、ずっと心に残っていました。使い込まれた木肌はほんのりと艶を帯び、手に取ると驚くほどすっと馴染む。軽くて扱いやすいプラスチックのものも増えてきたけれど、やっぱり私は木のぬくもりに触れていたいと思うのです。 どこのものか尋ねると、「宮島工芸製作所のしゃもじ」だと教えてくれました。広島出身の彼女は 「杓文字といえば広島でしょ」と得意げに話します。 広島では、しゃもじが昔から縁起物として親しまれています。「福をすくう」といわれる宮島杓子をつくり続ける宮島工芸製作所は、地元では誰もがよく知る工房で、丁寧な手仕事で長く使える道具をつくり続けています。 彼女のおばあちゃんもお母さんも、ずっと宮島工芸製作所のしゃもじを使ってきたのだとか。だから彼女にとって、この工房のしゃもじを選ぶのはごく自然なことなのです。そんな話を聞くと、使い心地のよさもきっと確かなものなのだろうと思いました。 宮島工芸製作所 ちょうど広島を訪れる予定があったので、「宮島工芸製作所」の工房を訪ねてみることにしました。島に渡る船が着くと、穏やかな海と心地よい潮風が迎えてくれます。 世界遺産・厳島神社の鳥居を望むその地に、工房はひっそりと佇んでいました。入り口には大きなしゃもじが飾られ、その姿からも長い歴史の深さを感じます。扉を開けると、木のやさしい香りがふわりと漂い、古い機械の音とともに、職人の手仕事が生み出すリズムが奥の作業場で途切れることなく続いていました。 工房に入ると、まず目に飛び込んでくるのは、壁一面に並んだしゃもじやヘラたち。形も大きさも用途もさまざまで、ひとつとして同じものがありません。「闘志」「必勝」と記されたものや、記念品としてつくられたものも並び、この工房が歩んできた年月と、人々がそこに込めてきた思いが伝わってきました。 しゃもじは「メシを取る」ことから「召し取る」に通じ、戦の場では勝利祈願の道具としても扱われたといいます。その背景を知ると、壁に掛けられた一つひとつが、願いや祈りをすくってきた証のようにも見えてきました。 棚には数えきれないほどの木型が整然と並んでいます。「すしベラ」「お玉」「バターナイフ」。手書きされた文字は、油性ペンのインクが少しかすれていて、そこにもまた歴史を感じます。用途に合わせて工夫を重ねてきた職人たちの思考と経験が、ひとつひとつの型に息づいているのが伝わってきました。 使っている木は、広島県北部の山々に自生するヤマザクラ。 宮島の近くで育つ木だからこそ、良質な素材を安定して手に入れられるのだといいます。堅くて弾力があり、長く使っても歪みにくいのがこの木のよさで、使い込むほどに赤みと深みが増していきます。その変化はまるで、自分だけの道具へと育っていくようで、ますます魅力的に感じられました。 一本の木から生まれるかたち 静かな空間には、木地を切る音や削る音が心地よく響き、淡い木の粉がふわりと舞っています。 工房の片隅では、職人さんが一枚の板を机に置き、鉛筆でしゃもじやヘラを型取りはじめていました。木目を読みながら、どの部分が持ち手になり、どの部分がすくう面になるのか、迷いのない動きで描いていく姿は、まるで木と対話しているよう。一枚の板にパズルのようにびっしりと型が描かれていく様子は、“木を余すことなく使いきる”という、この工房の流儀そのものだと感じました。 描いた線に沿って板を切り進めると、木の中からしゃもじやヘラのかたちが現れてきます。切り抜かれた木地は、まだ角ばったまま。 そこから職人さんが型を当てて厚みを調整し、丸みを削り出していくと、だんだん私たちの見慣れた道具の姿へと近づいてきました。木地と向き合うその背中には、積み重ねてきた年月と、ものづくりへの情熱がにじんでいます。 削りの工程が終わると、木地は研磨の職人さんのもとへ渡ります。ここからは、道具としての表情を整えるために、ひたすら木地と向き合う時間のはじまりです。 研磨前の木地に触れると、木そのものの息づかいがまだ残っているような、少し荒々しい手触りがあります。まず、粗い番手の紙やすりで形を整え、次第に細かな番手へと移りながら、ざらりとした面を丁寧に落としていく。「ここまでやるのか」と思うほど、何度も、何度も。そうしてようやく、手のひらにすっと吸い付く、あのなめらかさが生まれてくるのです。 ...
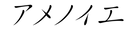
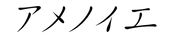






 青森県弘前「宮本工芸」の手仕事
青森県弘前「宮本工芸」の手仕事 丸両手付かご
丸両手付かご














